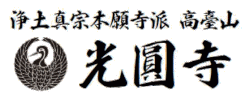シン(真)トイフハイツワ(偽)リヘツラ(諂)ワヌヲ
シン(真)トイフジチ(実)トイフハ
カナラ(必)ズモノヽミ(実)トナルヲイフナリ
親鸞聖人のお書きものには、ご左訓(さくん)といって、注意すべき言葉に解説を施して下さってあります。
智慧の光明はかりなし
有量の諸相ことごとく
光暁かぶらぬものはなし
真実明に帰命せよ
皆さんも、よくご存知の、お正信偈のお勤めをするときの第二首目の和讃です。
「真実」という言葉は、辞書を引きますと、おおよそ、①うそいつわりのないこと。②仏教用語で絶対の真理。とでてまいります。
ところで、ウィキペディアでは「真実は事実と同様で、皆が一致する一つの場合もあり、人それぞれに複数存在する場合もあるが、一般的には、他者との関係性を前提に社会で合意して共有できる皆が一致する、より公的で社会性を有する事柄を真実と言う」という民主主義的な説明が為されていて、ナルホドと感心させられる一方、これでいいのかな?と心配になります。
つまり、「真実は多数派の都合によっていかようにも変わりうるものである」ということです。
多数派に与したものが傍若無人(ぼうじゃくぶじん)に少数派を踏みにじってゆく。
「赤信号みんなで渡ればこわくない」ではないですが、国会で明らかにウソだろうという答弁がまかりとおり、「寄らば大樹の陰」とばかり権力に忖度(そんたく)し、偽(いつわ)り、諂(へつら)う者が出世をしていく現在の政治・社会状況を目の当たりにすると、怒髪(どはつ)天(てん)をつくような怒りを覚えます。
しかし、「怒り」には、自分もそうでありたいのにそうではない、ずるいじゃないか、許せない!というメカニズムが隠されているのだそうです。なんのことはない、自分を棚に上げて、他者を非難する事で自分をなぐさめているのです。
わが身を正義の立場において、他者を非難、弾劾する。その時の優越感、全能感は、まさに快感でもあります。ただし、その代償もしっかり求められます。正義の立場とは多数派だからです。常に多数派に属していなければ、不安でなりません。少数派に転落すれば、自らが非難、弾劾される側に回されてしまうからです。「いじめ」問題の本質もここにあるのではないかと感じています。いじめる側にいなければいじめられてしまうのです。
テレビのワイドショーでもインターネットでも、これでもか、というぐらい非難、中傷が繰り返されていて、うんざりします。昭和36年生まれの私には、「弱きを助け強きを挫く」ということが格好いい、という感覚がどこかに残っているのですが、権力者がやり玉に挙がる事は、ほぼなく、自分にしっぺ返しのくる心配の無い芸能人や一般人が、その対象です。嫌なら見なければいいだけなんですが、どのチャンネルもとなると選択肢もありません。

さて、前置きがずいぶん長くなってしまいましたが、親鸞聖人の「真実」の味わい方が、とてもありがたく思います。
「偽り諂わぬ」ということは人間の話ではない。仏さまの話なのだというのです。私たちにそうなれ、そうあらねばならぬ、と仏さまはおっしゃられない。
ただ、お上手、気休めもおっしゃりません。
なんぢはこれ凡夫(ぼんぷ)なり。心想羸劣(しんそうるいれつ)にして、いまだ天眼(てんげん)を得(え)ざれば、遠(とお)く観(み)ることあたはず。(観無量寿経)
何とも手厳しいお言葉に聞こえますが、「なんぢはこれ凡夫なり」と告げる時、「なんてダメな奴なんだ」と非難している訳ではないのです。あなたは、心が弱く劣っていて、将来の事がひとつも見通せない。だから、いつも不安で、至らぬ自分を認め、許し愛することなく、あいつは偽る、こいつは諂うと、他者に投影し、責め立ててしまう。あなたは立派ね、と常に他者から承認されたくてたまらない。けれども、それではいつまでたっても孤独で、恐れや不安から免れることは出来ないよ。
辛かろう、苦しかろう、私がここにおるよ。私にまかせておくれ。本当の安らぎをあなたに与えさせておくれ・・・。ナンマンダブツ。
仏さまは、他者を非難、弾劾するという事を一切なさいません。仏さまがなさらないのですから、私も、自らの弱さ、卑怯を他人に転嫁して責め裁かずともいいのです。
立派な人間を装う必要もありません。うらやましがられる必要もありません。「いいね」を押してもらわなくてもいいんです。
なんだ、そうなんだ!
なんだか、とっても安心する。
ナンマンダブツ。気がつけば、しっかりと充実した「実」が腹の座りとなっている。真実は、私の生きる核となって下さるのです。 称名