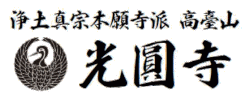物を申せば心底もきこえ、
また人にも直さるるなり。
ただ物を申せと仰せられ候ふ。
『大般涅槃経』の冒頭にこんなエピソードが出てきます(七不衰法)。
マガダ国の大臣が王様の命で、小国ながら商業の盛んなヴァッジ族を征服せんとする意志のあることを告げに来ます。お釈迦さまは大臣には直接答えず、弟子の阿難に問いかけます。
「阿難よ、ヴァッジ族の人々がしばしば会議を開き、会議には多くの人が集うということを、そなたは聞いたことがあるか?」
「はい。そのような話を私は聞いたことがあります」
以下、六つの問いに同じ答えを得て、大臣に告げます。
「私はかつてヴァッジ族に衰亡を来さない法を説いた。この七つが守られている限りはヴァッジ族には繁栄が期待され、衰亡することはないであろう」
大臣は「衰亡を来さない法を一つ具えているだけでも繁栄が期待され衰亡はないであろう。まして七つも具えていては(武力による)征服は無理である」と悟ります。
気になるのは、この後、大臣が「外交手段を用いるしかない(離間工作によって七不衰法を自ら手放させる)」とリアルにつぶやくところです。武力によって法が破られることはない、と経典は言いたいのですが、ヴァッジ族は、その後、どうなったのでしょうか?
* * *
さて、この様に、仏教徒は話し合いをとても大切にしてきました。その伝統は脈々と受け継がれます。
本願寺中興の祖、蓮如上人は、八代目の門主として様々な改革を行い、親鸞聖人のみ教えを今に伝える基礎を築いて下さいました。
その蓮如上人の金言が記録されている『蓮如上人御一代記聞書』に、「談合」という言葉が度々でてまいります(今では不正の代名詞のような使われ方をされてしまい、とても残念です)。
一句一言を聴聞するとも、ただ得手に法を聞くなり。ただよくきき、心中のとほりを同行にあひ談合すべきことなりと云々
わずかに短かい話であっても、人はそれぞれ受け止め方が違うものだから、自分がどの様に受けとめたかを仲間と話し合う事がとても大切な事だよ、と勧めて下さるのです。
とくに大切の「他力」の教えは、自分の常識を持ち出しては理解しがたい教えです。
蓮如上人仰せられ候ふ。物をいへいへと仰せられ候ふ。物を申さぬものはおそろしきと仰せられ候ふ。信・不信ともに、ただ物をいへと仰せられ候ふ。物を申せば心底もきこえ、また人にも直さるるなり。ただ物を申せと仰せられ候ふ。
ことは「後生の一大事」に関わることであるから、お上手を言っていても始まらない。自分の正直な想いを語りなさい。自分を深く知ることができるし、間違っていても直してもらえるチャンスだよ、と。
称名