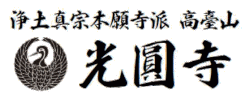如来大悲の恩徳は
身を粉にしても
報ずべし
師主知識の恩徳も
骨を砕きても
謝すべし
( 恩 徳 讃 )
ご法座の最後は、恩徳讃を唱和して締めくくられることが多く、そのメロディととも詩句も覚えて下さっている方も多いと思います。もともと、ご和讃は、字の読めない者にも覚えやすいようにと、今様(いまよう)という、抑揚をつけて誦(じゅ)することが出来る形式に整えられています。親鸞聖人の時代には、後鳥羽上皇が好まれたこともあり、庶民にも大流行したようです。現在では新節と呼ばれる洋楽の旋律で歌われることが多くなりましたが、旧節と呼ばれる哀調漂う雅楽の旋律を懐かしむ声もよく聞かれます(今回はそれを四部合唱で聴かせて頂きましたが、本当に、素晴らしかったですね)。本願寺は大きくは西・東に分かれていますが、その他にも高田派や仏光寺派など、親鸞聖人のお弟子を開基とする宗派があり、真宗十派連合会というような集まりでは旧節の恩徳讃が唱和されます。
ところで、この様に、大変、身近に感じるご和讃ですが、詩句自体は、大変、厳しいお言葉で、恐ろしげなご和讃と感じる方も多いのではないでしょうか?実は私もそうでした。直接の経験はなくても、戦争映画などで上官が「粉骨砕身努力せよ!」と部下を督励しているシーンは、その後の戦闘で、それこそ木っ端微塵にされる兵士の姿と合わせて、子ども心にも恐ろしく感じられたものです。
粉骨砕身とは『禅林類纂』に出て来る言葉ですが、その他にも粉身砕骨とか砕骨粉身と熟語する例もあり、宗祖は粉身砕骨を採られてご和讃されたと思われます。
ただ、宗祖のお書きものを拝読するときの注意点なのですが、「親鸞は弟子一人ももたず候ふ」と歎異抄に伝えられているように、教師として誰かに教えを垂れる、という態度をおとりになることはなかった、ということです。ですから、~すべし、とお書きになるときは、人に向かってではなく、自らに言い聞かせる言葉であった訳です。しかもニュアンスとしては、~せねばならない、ではなく、せずにはおれない、です。
では、粉身砕骨せずにはおれない、ところまで宗祖を駆り立てたものは何だったのでしょうか?
それが、如来大悲の恩徳です。
喜びもつかの間、苦しいこと、悲しいこと、悔しいこと・・・。理不尽な社会に怒り心頭の時もあった。このままでは、何のために生まれてきたのか分からない。あまりにも無念で、死ぬに死ねず、生きるには辛すぎる。
お前は死ぬんじゃない、我が国に生まれんと思え。あふれんばかりの光(智慧)の世界に迎え入れて、お前を仏にするぞ。・・・死ぬんじゃない、仏と成らせて頂くのだ。この仏さまの願いを聞き入れて、初めて自らの人生に尊い意味を見いだし、力強く生きることが出来たのです。
称名